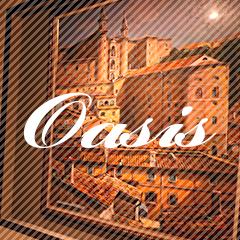-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
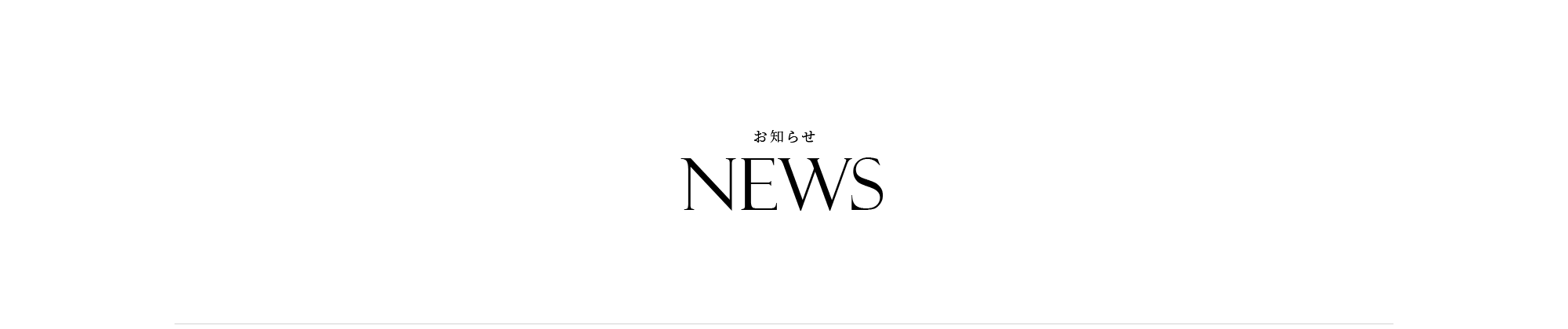
皆さんこんにちは!
ラウンジ Oasis、更新担当の中西です。
今回は、「ラウンジ」と呼ばれる夜のお店が、どのように誕生し、どんな歴史をたどってきたのかを深掘りしていきます。
キャバクラでもスナックでもない「ラウンジ」という独自の業態。そのルーツと、時代とともに変化してきたスタイルについて、一緒に見ていきましょう!
まず、「ラウンジって何?」という方のために、簡単に整理しておきましょう。
ラウンジは、キャバクラほどの派手さや積極的な営業がなく、スナックよりもやや高級感を持つ、大人向けの社交場です。
以下のように位置づけられることが多いです。
| 業態 | 接客スタイル | 料金形態 | お店の規模 | 客層 |
|---|---|---|---|---|
| スナック | ママ中心・気軽な会話 | チャージ+都度清算 | 小規模 | 地元の常連 |
| ラウンジ | 複数女性による接客 | セット料金制+ボトル | 中規模 | ビジネスマン中心 |
| キャバクラ | 指名・ドリンク営業 | 時間制+ドリンク営業 | 大規模 | 若年層〜経営者 |
ラウンジは、その中間的な立ち位置が最大の特徴で、「気楽だけど、上品」「距離は近いけど、押しつけがましくない」そんな絶妙なバランス感が人気です。
ラウンジという言葉が日本のナイトシーンで広く使われるようになったのは、1970年代後半〜1980年代です。
高度経済成長を経て、日本は豊かになり、ビジネスの場でも「接待」が活発に行われるようになります。
この時代、接待の場としてよく使われていたのは、高級クラブ。しかし、クラブは料金も高く、格式も高い。誰もが気軽に使える場所ではありませんでした。
一方で、スナックでは少しカジュアルすぎて、ビジネスの場には使いにくい。
その“間をとる存在”として生まれたのが、ラウンジなのです。
ラウンジは、クラブほど堅苦しくなく、それでいてスナックよりも洗練された空間。
このコンセプトが、30代〜50代の男性ビジネスマン層にヒットし、企業の接待や個人のリラックス空間として、各都市のビル街に次々と店舗が増えていきました。
バブル経済期(1986〜1991年)は、ラウンジの黄金期ともいえる時代です。
企業の接待費が潤沢にあり、営業マンや経営者がこぞってラウンジを利用。
この頃のラウンジは、クラブに近いラグジュアリー感を持ちながらも、より“通いやすい価格帯”で展開されていたのが特徴です。
また、ボトルキープ制度が定着し、名前で呼ばれる“常連感”が顧客の満足度を高め、安定したリピーターが育つようになりました。
バブル崩壊後の平成期には、接待文化の縮小や、お酒を飲む文化そのものの変化により、ラウンジ業界も打撃を受けます。
それでも根強く生き残ったのは、ラウンジが持つ「落ち着いた大人の空間」という魅力でした。
平成後半以降は、ラウンジも時代に合わせて変化していきます。
喫煙・非喫煙の明確化
働く女性スタッフの年齢層の広がり
サービスの多様化(英語対応や音楽付きなど)
ラグジュアリーラウンジ、和風ラウンジ、オーセンティックな雰囲気重視の店舗など、専門特化型が登場
令和に入ってからは、SNSでの発信や外国人観光客のニーズにも対応した“次世代ラウンジ”も増えてきました。
今やラウンジは、「ただ飲む場所」ではなく「空間と接客を味わう場所」へと進化しました。
歴史ある業態でありながら、時代と共に柔軟に形を変えているのがラウンジの真の強さと言えるでしょう。
次回は、そんなラウンジを**長く愛される店にするための“経営の鉄則”**について詳しくご紹介していきます!
次回もお楽しみに!